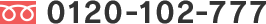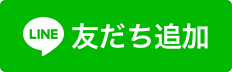相続登記義務化へ
- ※文字をクリックすると項目にジャンプします
目次
【相続登記義務化へ①】
不動産の相続や登記のルールが大きく変わろうとしています。令和3年2月10日、法制審議会は、相続登記や住所・氏名変更の登記を義務付ける法改正案を法相に答申しました。
改正案では、相続による不動産の取得を知ってから3年以内、住所や氏名の変更からは2年以内の登記を義務化し、正当な理由なく過怠した場合は、過料を科すものとしています。法務省は今国会中に関連法案を提出する方針です。(追記)令和3年4月、改正法案が成立しました。詳しくはこちら。
相続登記の義務化
現行の法制度において、相続登記(を含む権利の登記)は義務ではありません。
手続きが面倒だと先延ばしにしたり、相続人の協議がまとまらず登記を諦めるケースもあろうかと思います。資産価値がなく管理も難しい田舎の土地などは、放置せざるを得ない場合も多くみられます。相続登記を行わないでいると、時間の経過とともに関係者が死去したり、連絡がつかなくなったりして、相続人全員で協議を行うことが次第に困難となり、いっそう手続きが複雑化してしまいます。現在、日本の国土のうち所有者と連絡がつかなくなっている土地は400万ヘクタール以上にもなり、公共事業や土地の有効活用を大いに妨げています。そのうち約7割が相続登記の未了、3割が住所変更の不備によるものだそうです。
今回の改正要綱では、不動産所有者の相続人に対し、取得を知ってから3年以内の相続登記を義務付け、正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料を科す旨定めています。遺贈(相続人に対する遺贈)も同様とされます。この罰則は、当面は法施行後に発生した相続が対象になりますが、一定の猶予期間ののち、すでに発生している相続についても適用が広がる可能性があります。
住所・氏名変更登記の義務化
改正案では、転居や婚姻などで住所や氏名が変わった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務化され、正当な事由なく怠った場合、5万円以下の過料を科すこととされました。法人の本店移転の登記も同様とされます。
なお、法制審議会の改正要綱の中では、相続登記を推進するための仕組みづくりや、財産管理制度の見直し、不動産の国庫返納の制度新設なども提言されました。
【相続登記義務化へ②】
相続登記義務化①でご紹介した通り、令和3年2月10日、法制審議会は、相続登記や住所・氏名変更の登記を義務付ける法改正案を法相に答申しました。
改正案では、相続による不動産の取得を知ってから3年以内、住所や氏名の変更からは2年以内の登記を義務化し、正当な理由なく過怠した場合は、過料を科すものとされています。法務省は今国会中に関連法案を提出する方針です。今回は、相続登記義務化にむけた不動産登記法・民法の改正の動きについて、登記実務の観点から改正要綱の中身を詳しくご紹介します。
1.相続登記について
不動産の所有者の相続人は、取得を知ってから3年以内の相続登記を義務付けられ、正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料を科すという罰則規定が定められたことは、前回の記事でご説明したとおりです。
これに加えて、改正要綱は、法定相続分による相続登記がされていても、遺産分割によりその相続分を超えて持分等を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内にその登記を申請する必要があるとしました。ただし、法定相続分による相続登記が、嘱託や代位によってされた場合は適用外となります。
また、相続の発生をより登記に反映しやすくするための新しい仕組みとして、相続人の申出により登記官が行う「相続人申告登記(仮称)」を創設することが提言されています。
この制度では、相続人は、登記官に対し不動産の所有者が死亡した旨と、自らが相続人であることを申し出ることができ、登記官は職権で申出が行われた旨および申出を行った者の氏名・住所を登記するものとしています。相続人は少なくともこの申出を行えば、相続登記の義務を履行したとみなされます(ただし、その後に遺産分割が行われた場合は再度登記の義務が発生します)。2.遺贈の登記について
相続人に対する遺贈の登記(相続人に対する遺贈に限る)も、相続の登記と同様に、取得を知ってから3年以内の登記が義務付けられる予定です。ただし、登記手続きを簡略化するため、共同申請の原則の例外として、相続人に対する遺贈の登記は登記権利者が単独で申請できるようになる見込みです。
3.法定相続分による相続登記の変更について
法定相続分による登記を行いやすくするために、法定相続分による相続登記がされたのち、下記の登記を行う場合は、更正の登記により、登記権利者が単独で申請することができるものとされています。
- 遺産分割協議および審判または調停により持分等を取得したとき
- 他の相続人が相続の放棄をしたとき
- いわゆる「相続させる」遺言による登記
- 相続人に対する遺贈の登記
(参考)
法務省HP 法制審議会第189回会議(令和3年2月10日開催)配布資料2:民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案【PDF】
【相続登記義務化へ③】
相続登記義務化へ、閣議決定相続登記義務化への動きが着実に進んでいます。
令和3年3月5日、(相続登記義務化へ①、相続登記義務化へ②)で紹介した改正法案が閣議決定されました。政府は今国会中の成立を目指すとしています。改正案では、相続による不動産の取得を知ってから3年以内、住所や氏名の変更からは2年以内の登記が義務化され、正当な理由なく過怠した場合は過料が定められています。
政府はいま、相続登記の義務化に加え、不動産の国庫返納の制度新設、財産管理制度の見直しなどを行うことで、大きな社会問題になった“所有者不明土地”の解消を目指しています。今回の記事では、この不動産の国庫返納の制度について取り上げます。
相続土地の国庫帰属に関する制度創設 (相続土地国庫帰属法 (仮称) )
この制度は、一定の要件を満たしていれば、管理費相当額を納付のうえで、相続した土地を手放すことを認めるとする制度です。
申請人
申請権者は相続や遺贈(※)により土地を取得した所有者であり、申請人は、その土地を国庫に帰属させることについて“承認を求めることができる”とされています。
他に共有者がいる場合は、共有者の全員で行うことが必要です。相続以外の理由で持分を取得した共有者は、この場合に限ってのみ承認申請をすることができます。
※相続人に対する遺贈に限る。要件
国庫帰属が承認されるための主な要件は下記のとおりです。
①建物がないこと
②抵当権等の担保権や、使用・収益を目的とする権利(地上権・永小作権など)がないこと
③土壌汚染がないこと
④境界が明らかで、争いのないこと
その他、崖や勾配、樹木や工作物、埋没物などの管理や処分が困難になる要因や、事情がないことが求められます。管理費用
承認申請は法務大臣により審査され、必要の場合は法務局職員が調査を行います。申請が承認された場合、申請人はその土地の10年分の標準的な管理費用を負担しないといけません。承認申請人がこの負担額を納付すると、土地の所有権は国庫に帰属します。
管理費用は、用途や面積、周辺環境などに応じ政令で今後定められるとされています。
現時点での参考額ですが、国有地の標準的な10年分の管理費は、原野で約20万円、200㎡の宅地で約80万だそうです。* * *
現行の法制度においても、相続人が不存在であり、すべての清算を終わったのちにも残余した不動産は、国庫に帰属することになっています。この場合、相続財産管理人は残余不動産を所轄の財務局長に引き渡し、国は管理人が作成した引継書に基づき所有権移転登記を行うことになります。
しかしながら、実際のところ不動産が不動産のまま国庫に引継ぎされるのはかなりのレアケースであり、実務上は相続財産管理人が権限外行為許可を得て売却(換価)したうえで、現金を家庭裁判所に納入するという手続きがとられることが一般的です。今回の改正法案は、相続土地を不動産のまま国庫帰属させるための制度を具体的に定めたという点で画期的といえます。しかしながら、その要件を満たす土地は相続不動産全体のごく一部と思われ、承認申請もかなり困難なものになることが予想されます。
(参考)
法務省HP 法制審議会第189回会議(令和3年2月10日開催)
配布資料2:民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案【PDF】関連ページ:
〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)
広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
当法人は、広島市佐伯区五日市の方々から多くのご相談を頂いております。
その他中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、廿日市市の方々のご相談も受け付けておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言書作成でお困りの方はぜひご相談ください。